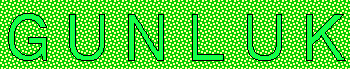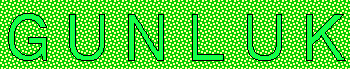2025年 4月 13日(日)午前 7時 52分
昨日は、土曜日なのに、神戸で美術館のハシゴをした。そんなに混まない美術館だからという判断だったが、往きの阪神電車が、わりと混んだので、続けない方がいいかもとは思う。これだと、帰りは、腰が大変になってるだろうに、大丈夫かなと思ってたら、帰りの方が、電車は空いていた。だから、昨日は、無事に帰って来れました。で、その行程は、まずは横尾忠則現代美術館、ここへ行くときは、阪神岩尾駅から歩いて行く。2時間かかるので、ここへ行くときは、美術館の近くに見つけてある定食屋さんで、お昼を食べてから行動開始にしている。土曜日だったので、混んでたけど、無事に食べることができた。次いで、JRで住吉駅まで移動してから六甲ライナーで、神戸市立小磯記念美術館へ。阪神電車を使った方が安上がりなんだけど、六甲ライナーに住吉駅から乗ろうの魂胆で、そうした。実は、この移動では、王子公園の脇を通り、人がいっぱいで、このお出かけは、完全にミスったかと思った。先日のお出かけから、桜の季節だということを、全く考慮しないで行動している。昨日も、王子公園近くまで来て、やってもたの気になったのだ。それ、遅いよね。だから、かなり、帰りは諦めモードだったんだけど、助かった。運がある、まだ。
横尾忠則現代美術館は2回目。前回は、「寒山百得」が出たときだったが、そのあと、あの連作、東京国立博物館所蔵になったんだね。あのニュースには、びっくりしたな。で、今回は「横尾忠則の人生スゴロク展」というものだった。行くまで、全く、想定してなかった展示だった。横尾忠則の誕生から、ここまで90年かな、その人生を、時系列的に追いかけるというもの。作家活動を始める、当然、イラストレーターとしてだが、それまでは、横尾忠則自身が、振り返り、描いたものが並んでる、もちろん、イラストレーター時代の作品、人気が出過ぎて、疲れからか、精神世界に没頭して、繰り返しインドに行っていた頃の作品、そして、画家宣言、画家宣言後も、そのスタイルが、時々の関心からか、変化を遂げる。阪神大震災の影響も大きい。先日行った兵庫県美のコレクション展にも、横尾忠則の描いた震災からの復興を願うポスターが出てたしと、この人、基本的に、自らの故郷に対する思い入れが大きいところがある。折に触れ、故郷西脇の思い出を、描く素材に使っている。そして、「寒山百得」から90歳の今の作品で締めくくるという構成。それを、スゴロクに模しての展示という工夫。気に入ったかどうかは別にして、色々と気になったり、どうしても記憶に残ってしまったり、そんな作品をメモっておく。子どもの頃のお気に入りだったのでしょう、武蔵と小次郎を描き込んだ「大入り満員」、この人、実の親と育ての親がいるそうで、刈萱の物語を思い出しては、実の親を求めるようなことがあったことを描いた「御神裁」、殺人事件が近くであり、その司法解剖が民家の庭先であったことを描いた「今夜の酒には骨がある」、「1944年、私は夢で龍に出会った」で描かれた電信柱に巻き付いた龍の姿は、別格の写実だった。空襲の思い出を描いた「回転する家」、作家活動を始めるため自己PRのために描いた「Tadanori Yokoo(自主制作)」、イラストレーターとしてのヒット作は、この企画展だけではなく、4階のコレクション・ルームにも展示されていた。有名なものなので割愛、ただ、傑作だったのは、作品とともにジグソーパズルも作り売ってたんじゃないかな? 三島との親交があったようで、その死に当たって描いた「男の死あるいは三島由紀夫よR.ワグナー」では、三島とワグナーが共存してる。画家宣言をして間もなく、ボディビルダーとのコラボをしている、モデルにした作品が3点出てたが、「Lisa Lyon in izukogen March 23, 1984(No.2)」が、抜群に気になった作品。木々や葉、水の流れをデザイン化したかのような形状に惹かれた。キャプションには″新表現主義‶と書かれていた作品群は、その他の作品と、明らかに一線を画す激しさ、過度の抽象表現が目立った。キャンパスに蛍光灯を仕込んだり、キャンパスへの細工が入ったりと、他の時代には看れないものがあった。「死者の誕生」は「赤」のシリーズ。「暗夜行路」は「Y字路」シリーズ。同じ「Y字路」シリーズでも、「黒いY字路1」では、1度、描いた絵の具を拭きとっている。鬱屈とした空気感が出ている。「城崎幻想」は「温泉」シリーズ。上手いと、大向こうから声がかかりそうな写実的でありながら幻想的でもある。「黄金の荒野に北極光」「N.P」は、この美術館の開館に当たり、横尾忠則が、ライブで制作したものとか。幾つかの風景を重ねている。「N.P」では、この美術館が描き込まれている。この重ねということに気が付いたとき、この人の頭のなか、どうなってるんやと思う程の認識眼に想像力。そして、再び、武蔵と小次郎が現れ、この人生スゴロクも終わりに近づいて行った。かなりの変化のある作家人生。それらを細かく観るためには、ここへ、足繫く通わねばならないね。そう思わせられた展覧会だった。
小磯良平美術館の展示は、特別陳列 「戦後神戸の女性画家二人展 松本奉山・中島節子―日本画・洋画 抽象の試み―」をメーンに据えてのもの。2つ目の部屋では「画家たちの眼と小磯良平素描選」と題するコレクション展があった。3つ目の部屋は、お約束の小磯良平もので固められていた。お題にもある作家お二人、全く知らなかった。だから、行こうの気になった。それは、大正解。なかでも、松本奉山、こんな作風の人がいたんだの思い。この人、今年が生誕100年というアニヴァーサリー・イヤーだということで、他のミュージアムでも、回顧展があるので、即決、行きます。水墨のプロパーで、伝統的な山水とか、そういったものではなく、同じ風景画でも、めっちゃ写実からスタートしてる。冒頭にあった「分水嶺」を観て、びっくりした。知らない世界だった。とっても、繊細な筆致で、写実に徹している、それを、水墨でやってた。そして、この人、ある日、アメリカに水墨の指導とかデモンストレーションで行き、一気にタッチが変わる。アメリカの風景、都市、田舎問わず、水墨での表現としての方針が変わる。エッセンスを、研ぎ澄ました感性で選び出し、それだけを描くというスタイルへとなる。圧巻は「エンパイヤステートビルディング」、筆致の勢いと、省略という手で、上昇感を表し、高層ビルを表していた。「夏のセントラルパーク」では、水墨で光の表現まで試みている。凄い着想だし、成し遂げている。このスタイルを持ち、この人、世界を歩き、描いている。もう一つの圧巻、それには、唖然という言葉も添えねばならないけど、「テムズ河遠望」という作品。キャンパスのかなり上部に橋らしきものが、薄墨で描いてあるだけ。それより下は白紙、それがたゆとう川の流れになっている。水墨で、こんな人、いるなんて! これを、日本の風景にも適用したのが「竜田川」というお題の2点。だが、これは、しんどかった、正直。錦織りなす紅葉は、きつい。何よりも、日本のウエットな風土に合ってないような気がした。仏画にも使っていた。もう、一切の無駄を省いた表現で、抽象画かと、お題を見ないで観ると、思ったかもしれない。とにかく、おもしろい! いい作家さん、教えてもらえた。一方の中島節子は、洋画で、小磯良平門下との紹介が、キャプションにはあったけど、作風は、パンリアルの雰囲気。人を描いた作品が多いんだけど、身体のパーツを、デフォルメしており、頭は小さく、三角状、いや、その変形かな。手が大きかったり、脚が長かったり、描きたい素材、テーマに合わせて、その辺の振幅を図ってるように観えるのもあれば、そうでないものもあるので、何やらの基準があるのかどうかが掴めなかった。色彩は、無彩色系、タッチも、地の部分は粗くしてあるから、ますます、パンリアルの鳥の絵を描いた下村良之介作品を思い出していました。2つ目の部屋に入る。前半分は、信濃橋研究所などで学んだ作家さんらの洋画が並ぶという、前回同様の展示。気になったものだけ、ピックアップしておく。金山平三「安茂里」だけど、せっかく、先日、兵庫県美で金山作品、気に入ったと思えるようになったのだが、また、元の木阿弥。関口俊吾という作家さん、初めてだと思うけど、このコーナーでは、一番、目立ってたかもしれない。鹿子木孟郎門下だそうだ。4点出てたが、「オンフルール」というフランスの地方の村の一角を描いた作品、えらく地面を広く取った構図だけど、マチエールで、ごつごつと、えらくリアルなのに惹かれた。お隣の「ガルダイア(アルジェリ)」が、遠目で観ると、えらく映える。近くで観ていたとき、壁の白さに引いてしまってたけど、遠目で観ると、それが街に収まっている。下町のごちゃごちゃ感に、うまく収まり、こちらもリアリティを感じさせられた。横の「アムステルダム」も遠目で観ないと、描かれている場所の広さを感じさせられない。でも、オランダにしては、質素さが、いまいち欲しい。黒い館、もう2~3軒多いと、オランダが身近になるのにと思いながら観ていました。桝井一夫「石切場(C)」は、雄大。大きな絵だけど、その大きさ以上に大きい。同じく「焼岳」の写実に徹した山に対して、裾野の木々がデザインチック。これも、遠目で観た方が、その木の描き方の意味が了解できる。鴨居玲が2点、「風船と女」「石の花」、難解な作品です。背景があるのかな? 女の髪が風に吹かれてるのに、風船は止まったように浮いてたり、裸の男女が抱き合っていたり、何かがあるのでしょうね。古家新は、今回もいいなと思う。「ブルターニュの小村」「黎明」が出てた。今井朝路「唄ふ彼」は、2つの顔で1つの顔? ピカソみたい。後半は、小磯良平の素描。前回もそうだったけど、小磯良平になると、一気にグレードが上がったと思ってしまう。人物画で、特にそう思う。身体の存在感が違う。内面が気になる。風景だと、遠近感を徹底している。安定していると言えるからだ。特に気に入ったものだけメモっておく。「月光」「琉球所見スケッチ 荷車のある風景」「母子像(B)」「オーヴェル風景」「サンタ・マリア・デルラ・サルーテ」「バイオリンを弾く女」「リュートを持つ男」。「小豆島の風景」では、透視図法用の線まで残っていた。貴重な展示に感謝。第3室は小磯良平の部屋。前回から展示替え。前の方がおもしろかったかな。ここでも、人物画に惹かれた。「自画像」「青衣の女」「洋和服の二人」「着物の女」「肩掛けをした少女」が、めっちゃ目立つ。「青衣」「洋和服」「着物」と着ているものを描くのも、上手いなぁ。「着物の女」の縦縞なんて、最高だ。モデルの女性の気質まで出ていそう、その着物で。風景画では、「神戸風景」「オリーブ園(小豆島)」「森」が推し。「森」は、前回も出てたけど、絵の中に迷い込んだ女が一人という感じを、今回は持ってしまった。変化技が「マヌキャン」、顔はマネキンだけど、身体は生身の人間のようで、背筋がこそばくなってしまった作品だった。この美術館、これだけ遊ばしてもらって、入場料200円とはコスパ良すぎです。また、行きます。第3室は、ホント、楽しみだからね。 |