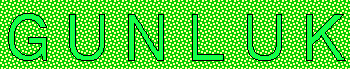
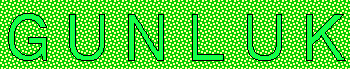
トルコのこと、キプロスのこと、こんなことを主に、日々思うこと。ときどき、韓国のこと、
日本のことも混じるかも? 仕事に忙しくっても、頭のなかは、トルコのこと、キプロスのこと考えてる。
頭のなかは、いたって長閑。それが、、、、、、 |
2016年 1月 6日(金)午前 0時 15分 |
2016年 1月 4日(水)午後 11時 3分 |
2016年 1月 3日(火)午後 10時 46分 |
2016年 1月 2日(月)午後 9時 56分 |
2016年 1月 1日(日)午後 9時 33分 |
2016年 12月 31日(土)午後 8時 35分 |
2016年 12月 31日(土)午前 7時 44分 |
2016年 12月 30日(金)午前 7時 12分 |
2016年 12月 28日(水)午後 10時 34分 |
2016年 12月 27日(火)午後 10時 52分 |
2016年 12月 26日(月)午後 11時 7分 |
2016年 12月 25日(日)午後 11時 10分 |
2016年 12月 24日(土)午後 10時 53分 |
2016年 12月 23日(金)午後 11時 00分 |
2016年 12月 22日(木)午後 10時 21分 |
2016年 12月 21日(水)午後 10時 37分 |
2016年 12月 20日(火)午後 10時 56分 |
2016年 12月 19日(月)午後 11時 36分 |
2016年 12月 18日(日)午後 10時 34分 |
2016年 12月 17日(土)午後 10時 54分 |
2016年 11月 22日(火)午後 10時 49分 |
2016年 11月 21日(月)午後 11時 23分 |
2016年 11月 21日(月)午前 7時 11分 |
2016年 11月 20日(日)午前 7時 00分 |
2016年 11月 18日(金)午後 10時 58分 |
2016年 11月 17日(木)午後 11時 35分 |
2016年 11月 17日(木)午前 0時 15分 |
2016年 11月 15日(火)午後 9時 19分 |
2016年 11月 14日(月)午後 6時 49分 |
2016年 11月 14日(月)午前 7時 36分 |
2016年 11月 13日(日)午前 5時 18分 |
2016年 11月 12日(土)午前 5時 53分 |
2016年 11月 11日(金)午前 4時 57分 |
2016年 11月 9日(水)午後 10時 58分 |
2016年 11月 9日(水)午前 7時 18分 |
2016年 11月 7日(月)午後 11時 44分 |
2016年 11月 6日(日)午後 7時 10分 |
2016年 11月 6日(日)午前 4時 53分 |
2016年 11月 4日(金)午後 10時 23分 |
2016年 11月 4日(金)午前 5時 29分 |
2016年 11月 3日(木)午前 0時 3分 |
2016年 11月 1日(火)午後 9時 24分 |
2016年 10月 31日(月)午後 7時 49分 |
2016年 10月 30日(日)午後 7時 24分 |
2016年 10月 29日(土)午後 11時 34分 |
2016年 10月 29日(土)午前 6時 40分 |
2016年 10月 27日(木)午後 10時 42分 |
2016年 10月 26日(水)午後 10時 34分 |
2016年 10月 26日(水)午前 1時 1分 |
2016年 10月 24日(月)午後 7時 38分 |
2016年 10月 24日(月)午前 3時 40分 |
2016年 10月 22日(土)午後 11時 32分 |
2016年 10月 22日(土)午前 5時 1分 |
2016年 10月 20日(木)午後 10時 34分 |
2016年 10月 19日(水)午後 11時 00分 |
2016年 10月 18日(火)午後 10時 39分 |
2016年 10月 17日(月)午後 11時 10分 |
2016年 10月 16日(日)午後 6時 39分 |
2016年 10月 16日(日)午前 0時 6分 |
2016年 10月 14日(金)午後 10時 31分 |
2016年 10月 13日(木)午後 11時 49分 |
2016年 10月 12日(水)午後 11時 6分 |
2016年 10月 11日(火)午後 11時 23分 |
2016年 10月 10日(月)午後 7時 24分 |
2016年 10月 9日(日)午後 6時 14分 |
2016年 10月 9日(日)午前 2時 48分 |
2016年 10月 7日(金)午後 10時 37分 |
2016年 10月 6日(木)午後 10時 26分 |
2016年 9月 11日(日)午後 7時 9分 |
2016年 9月 11日(日)午前 7時 57分 |
2016年 9月 10日(土)午前 1時 19分 |
2016年 9月 9日(金)午前 0時 7分 |
2016年 9月 7日(水)午後 9時 33分 |
2016年 9月 6日(火)午後 11時 34分 |
2016年 9月 5日(月)午後 10時 49分 |
2016年 9月 4日(日)午後 11時 2分 |
2016年 9月 4日(日)午前 5時 26分 |
2016年 9月 3日(土)午前 0時 2分 |
2016年 9月 1日(木)午後 10時 59分 |
2016年 9月 1日(木)午前 3時 11分 |
2016年 8月 30日(火)午後 11時 55分 |
2016年 8月 29日(月)午後 11時 18分 |
2016年 8月 29日(月)午前 7時 1分 |
2016年 8月 27日(土)午後 10時 54分 |
2016年 8月 26日(金)午後 11時 22分 |
2016年 8月 26日(金)午前 6時 27分 |
2016年 8月 25日(木)午前 6時 3分 |
2016年 8月 23日(火)午後 11時 6分 |
2016年 8月 22日(月)午後 11時 26分 |
2016年 8月 21日(日)午後 11時 20分 |
2016年 8月 21日(日)午前 0時 26分 |
2016年 8月 19日(金)午後 11時 7分 |
2016年 8月 19日(金)午前 6時 34分 |
2016年 8月 17日(水)午後 10時 32分 |
2016年 8月 16日(火)午後 10時 53分 |
2016年 8月 15日(月)午後 11時 17分 |
2016年 8月 14日(日)午後 9時 59分 |
2016年 8月 14日(日)午前 5時 52分 |
2016年 8月 12日(金)午後 10時 44分 |
2016年 8月 12日(金)午前 4時 22分 |
2016年 8月 11日(木)午前 7時 54分 |
2016年 8月 9日(火)午後 11時 17分 |
2016年 8月 8日(月)午後 10時 36分 |
2016年 8月 8日(月)午前 4時 3分 |
2016年 8月 7日(日)午前 5時 23分 |
2016年 8月 6日(土)午前 7時 3分 |
2016年 8月 5日(金)午前 1時 48分 |
2016年 8月 3日(水)午後 11時 21分 |
2016年 8月 2日(火)午後 9時 57分 |
2016年 8月 2日(火)午前 7時 18分 |
2016年 7月 31日(日)午後 10時 38分 |
2016年 7月 30日(土)午後 7時 27分 |
2016年 7月 29日(金)午後 11時 26分 |
2016年 7月 28日(木)午後 10時 57分 |
2016年 7月 27日(水)午後 11時 18分 |
2016年 7月 27日(水)午前 7時 56分 |
2016年 7月 15日(金)午後 10時 24分 |
2016年 7月 14日(木)午後 10時 42分 |
2016年 7月 13日(水)午後 10時 33分 |
2016年 7月 12日(火)午後 11時 4分 |
2016年 7月 12日(火)午前 7時 20分 |
2016年 7月 10日(日)午後 10時 39分 |
2016年 7月 10日(日)午前 5時 35分 |
2016年 7月 9日(土)午前 5時 52分 |
2016年 7月 8日(金)午前 5時 52分 |
2016年 7月 6日(水)午後 11時 13分 |
2016年 7月 5日(火)午後 10時 54分 |
2016年 7月 4日(月)午後 10時 50分 |
2016年 7月 4日(月)午前 1時 29分 |
2016年 7月 3日(日)午前 5時 15分 |
2016年 7月 1日(金)午後 9時 34分 |
2016年 6月 30日(木)午後 10時 8分 |
2016年 6月 29日(水)午後 10時 26分 |
2016年 6月 28日(火)午後 10時 21分 |
2016年 6月 27日(月)午後 7時 52分 |
2016年 6月 27日(月)午前 4時 44分 |
2016年 6月 26日(日)午前 4時 38分 |
2016年 6月 25日(土)午前 0時 18分 |
2016年 6月 22日(水)午後 11時 3分 |
2016年 6月 21日(火)午後 7時 12分 |
2016年 6月 20日(月)午後 8時 57分 |
2016年 6月 19日(日)午後 7時 44分 |
2016年 6月 19日(日)午前 4時 31分 |
2016年 6月 17日(金)午後 9時 5分 |
2016年 6月 16日(木)午後 10時 41分 |
2016年 6月 15日(水)午後 10時 53分 |
2016年 6月 14日(火)午後 10時 9分 |
2016年 6月 13日(月)午後 11時 00分 |
2016年 6月 12日(日)午後 8時 2分 |
2016年 6月 11日(土)午後 10時 12分 |
2016年 6月 10日(金)午後 11時 57分 |
2016年 6月 9日(木)午後 8時 14分 |
2016年 6月 8日(水)午後 7時 56分 |
2016年 6月 7日(火)午後 11時 33分 |
2016年 6月 6日(月)午後 11時 44分 |
2016年 6月 5日(日)午後 7時 26分 |
2016年 6月 4日(土)午後 7時 11分 |
2016年 6月 3日(金)午後 11時 25分 |
2016年 6月 2日(木)午後 11時 32分 |
2016年 6月 2日(木)午前 5時 2分 |
2016年 5月 31日(火)午後 7時 6分 |
2016年 5月 30日(月)午後 11時 28分 |
2016年 5月 30日(月)午前 4時 13分 |
2016年 5月 27日(金)午後 11時 4分 |
2016年 5月 27日(金)午前 0時 27分 |
2016年 5月 25日(水)午後 11時 14分 |
2016年 5月 24日(火)午後 11時 20分 |
2016年 5月 23日(月)午後 5時 17分 |
2016年 5月 21日(土)午後 11時 10分 |
2016年 5月 20日(金)午後 10時 25分 |
2016年 5月 19日(木)午後 11時 24分 |
2016年 5月 19日(木)午前 0時 8分 |
2016年 5月 17日(火)午後 11時 29分 |
2016年 5月 16日(月)午後 11時 18分 |
2016年 5月 15日(日)午後 6時 27分 |
2016年 5月 9日(月)午前 0時 34分 |
2016年 5月 8日(日)午前 2時 13分 |
2016年 5月 6日(金)午後 11時 39分 |
2016年 5月 4日(水)午後 7時 53分 |
2016年 5月 3日(火)午後 11時 27分 |
2016年 5月 2日(月)午後 11時 49分 |
2016年 5月 1日(日)午後 9時 32分 |
2016年 4月 30日(土)午後 7時 32分 |
2016年 4月 29日(金)午後 10時 58分 |
2016年 4月 28日(木)午後 11時 47分 |
2016年 4月 27日(水)午後 11時 46分 |
2016年 4月 26日(火)午後 11時 26分 |
2016年 4月 25日(月)午後 11時 56分 |
2016年 4月 24日(日)午後 10時 13分 |
2016年 4月 23日(土)午後 10時 49分 |
2016年 4月 22日(金)午後 7時 16分 |
2016年 4月 21日(木)午後 11時 40分 |
2016年 4月 20日(水)午後 11時 31分 |
2016年 4月 19日(火)午後 11時 2分 |
2016年 4月 18日(月)午後 11時 35分 |
2016年 4月 17日(日)午後 11時 4分 |
2016年 4月 16日(土)午後 11時 47分 |
2016年 4月 15日(金)午後 11時 45分 |
2016年 4月 14日(木)午後 11時 14分 |
 |
 |
 |